個人番号(マイナンバー)制度について
- 目次のリンク先から戻る際は、右下に表示される「PAGE TOP」をご利用ください。
- 1.個人番号(マイナンバー)・身元確認書類について
- 2.マイナンバーを利用した情報連携による所得確認
- 3.オンライン資格確認
- 4.マイナンバーに関するお問い合わせ
1個人番号(マイナンバー)・身元確認書類について
国民健康保険法により医療保険者として認可されております弁護士国保は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」において、「個人番号利用事務実施者」とされております。
国民健康保険法施行規則により、国民健康保険組合への各種届出書及び各種給付の申請書にマイナンバーの記載が必要とされております。届出書は、当組合ホームページの「申請書一覧」からダウンロードし、ご利用ください。
マイナンバーをご記入いただいた場合、従来の必要書類に加え、組合員の本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の添付が必要になります。
なお、マイナンバーがわからない場合など、記載が困難な場合は、マイナンバーの記載が無くても届出を受理し、情報連携により手続きを行います。この場合は個人番号確認書類は添付不要です。
本人確認とは①番号確認、②身元確認の2つからなります。
| ①番号確認 (マイナンバーが正しいことの確認) |
②身元確認 申告者(組合員)が個人番号の正しい持ち主であることを確認 |
|
|---|---|---|
| A | マイナンバーカード 裏面で番号確認、表面で身元確認ができます | |
| B | 「世帯全員」と記載がある住民票(個人番号の記載あり・発行から3ヶ月以内)
|
顔写真付き身分証 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど 顔写真付き身分証がない場合 公的機関発行の書類の写しが必要になります。 年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本、納税証明書、資格確認書など |
| C | 個人番号通知カード(下記☆参照)
|
|
A ~ C いずれかの組み合わせが本人確認の書類となります。
マイナンバーカードがあれば、裏面で番号確認、表面で身元確認ができます。
なお、マイナンバーを変更(平成27年10月以降)された際は、14日以内に届出が必要となります。必ず当組合までご連絡をお願いいたします。
☆個人番号通知カードについて
令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わり、個人番号通知カードの新規発行(出生、海外からの転入)や再交付は廃止となりました。個人番号通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ、引き続き個人番号通知カードでマイナンバーを証明する書類として使用できます。
なお、「個人番号通知書」は、「マイナンバーを証明する書類」として利用することはできません。
2マイナンバーを利用した情報連携による所得確認
厚生労働省の通知により平成30年10月からマイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始され、70歳以上の方の一部負担金の割合の判定、高額療養費支給に係る所得区分の判定は、番号利用法等により個人番号の情報連携による所得確認を行うこととされています。 ただし、何らかの事由で個人番号の情報連携で一部負担金の割合や所得区分の確認ができない場合は、所得を確認する証明書のご提出を求める場合があります。
3オンライン資格確認
オンライン資格確認とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」とします)に基づき構築されたネットワークシステムを活用し、医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。
保険者が情報連携により所得情報を取得し、70歳以上の方の一部負担金の割合、高額療養費支給に係る所得区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行っております。
また、マイナポータルを通じて、特定健診・過去の受診歴・診療情報を閲覧できるため、その情報を基に医師や薬剤師と健康状況を共有でき、より正確な情報に基づいた診療や服薬指導等をうけることができます。
なお、オンライン資格確認で特定健診情報を保険者間で引き継ぐこととなっておりますが、前保険者の特定健診情報の取得を同意しない場合は、弁護士国保までお申し出ください。
参考 国民健康保険法(抜粋)
第三十六条 3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
4マイナンバーに関するお問い合わせ
- 公式サイト
-
- マイナンバーカード総合サイト
最新情報はホームページをご確認ください。
- マイナンバーカード総合サイト
| マイナンバー総合 フリーダイヤル(無料) |
0120-95-0178 ※おかけ間違えのないよう、ご注意ください。 |
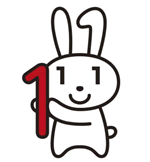 |
|---|
- ※平日:9時30分~20時 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始を除く)
- ※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
| 1番 | マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ ※年末年始を含む平日・土日祝ともに9:30~20:00(期間:令和2年12月~令和5年9月) |
|---|---|
| 2番 | マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難について |
| 3番 | マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ |
| 4番 | マイナポータル・健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ |
| 5番 | マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ ※年末年始を含む平日・土日祝ともに9:30~20:00(期間:令和2年12月~令和5年9月) |
| 6番 | 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ |
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
| 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) | 0570-783-578 |
聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号
| 聴覚障がい者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。回答については「個人番号カードコールセンター」からFAXで送信します。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。 | 0120-601-785 |
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
| マイナンバー制度、マイナポータルに関すること | 0120-0178-26 |
| 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止について | 0120-0178-27 |
| マイナポイントに関すること | 0570-028-125 |