医療機関等を受診するとき
療養の給付
疾病や負傷で医療機関、調剤薬局等を受診するとき、保険証、資格確認書、または保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(オンライン資格確認等に係る機器が整備された医療機関等に限る)を提示すれば、診察、投薬、処置、調剤等の療養の給付を受けることができます。療養の給付を受ける方は、その給付を受ける際、当該給付に要する費用の一部を保険医療機関等に支払います(一部負担金)。
医療機関の設備の関係上、マイナ保険証で受診できない医療機関の場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することにより、受診可能となっております。(資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することはできません。)
70歳から74歳の方でマイナ保険証をお持ちでない方は、弁護士国保組合が交付する保険証または資格確認書とともに、「国民健康保険高齢受給者証」の提示が必要です。
- 目次のリンク先から戻る際は、右下に表示される「PAGE TOP」をご利用ください。
- 1.保険医療機関等に受診された際の一部負担金
- 2.入院時食事療養費の標準負担額
- 3.入院時生活療養費
- 4.保険外併用療養費
- 5.長期収載品の処方又は調剤に係る選定療養における患者の特別負担について
1保険医療機関等に受診された際の一部負担金
1未就学児
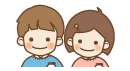 |
2割負担 | 小学校入学前の3月31日まで (6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日まで) |
2小学生から69歳の方
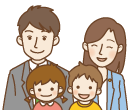 |
3割負担 | 小学校入学の4月1日から70歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日である場合はその前の月)まで |
370歳以上75歳未満※1
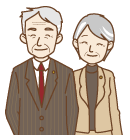 |
2割負担 (一般所得者等) |
70歳の誕生日の属する月 の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後75歳の誕生日の前日 まで |
| 3割負担 (現役並み所得者) |
- 70歳以上75歳未満の一部負担金の割合に係る所得区分、給付割合の決定方法等について、詳しくはこちらをご覧ください。
- ※自己負担額が同一月に一定額を超えた場合は、「高額療養費」としてその超えた額が支給されます。
2入院時食事療養費の標準負担額
入院中の食費は、療養の給付とは別に療養費として位置づけられ、食事療養に要した費用のうち、下記の「標準負担額」が自己負担となります。残りの費用は、弁護士国保組合が「入院時食事療養費」として負担します。
住民税非課税世帯の場合には、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」による申請が必要です。弁護士国保組合にお届けください。情報連携で被保険者全員分の所得情報を確認しますが、取得できない場合には、世帯全員分の住民税非課税証明書の提出が必要になります。
| 区分 | 食事療養標準負担額 (1食につき) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||||
| A | B、C、Dのいずれにも該当しない方 | 460円 | 490円 | 510円 | ||
| B | C、Dのいずれにも該当しない方で
|
260円 | 280円 | 300円 | ||
| C | 非課税 |
|
過去1年間の入院期間が90日以内 | 210円 | 230円 | 240円 |
| 過去1年間の入院期間が90日超 | 160円 | 180円 | 190円 | |||
| D | 低所得者Ⅰ(70歳以上で、被保険者全員が住民税非課税である世帯に属し所得が一定基準※以下の方) | 100円 | 110円 | 110円 | ||
- ※一定基準以下とは、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収806,700円以下、(2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下(夫婦各々年収806,700円以下))の方が該当します。
3入院時生活療養費
療養病床(病状が安定期にあり、主として長期にわたり療養を必要とする方の病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の「標準負担額」が自己負担となります。残りの費用は、弁護士国保組合が「入院時生活療養費」として負担します。
指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者以外の者
| 区分 | 生活療養費標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 居住費(1日) | 食費(1食) | |||
| 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||
| 一般(低所得者以外の方) (入院時生活療養費Ⅰ) |
370円 | 460円 | 490円 | 510円 |
| 一般(低所得者以外の方) (入院時生活療養費Ⅱ) |
370円 | 420円 | 450円 | 470円 |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
370円 | 210円 | 230円 | 240円 |
| 低所得Ⅰ (年金806,700円以下等) |
370円 | 130円 | 140円 | 140円 |
| 境界層該当者 | 0円 | 100円 | 110円 | 110円 |
厚生労働大臣が定める者
| 区分 | 生活療養費標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 居住費(1日) | 食費(1食) | |||
| 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||
| 一般(低所得者以外の方) (入院時生活療養費Ⅰ) |
370円 | 460円 | 490円 | 510円 |
| 一般(低所得者以外の方) (入院時生活療養費Ⅱ) |
370円 | 420円 | 450円 | 470円 |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
370円 | 210円
|
230円
|
240円
|
| 低所得Ⅰ (年金806,700円以下等) |
370円 | 100円 | 110円 | 110円 |
| 境界層該当者 | 0円 | 100円 | 110円 | 110円 |
指定難病患者
| 区分 | 生活療養費標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 居住費(1日) | 食費(1食) | |||
| 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||
| 一般(低所得者以外の方) | 0円 | 260円 | 280円 | 300円 |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
0円 | 210円
|
230円
|
240円
|
| 低所得Ⅰ (年金806,700円以下等) |
0円 | 100円 | 110円 | 110円 |
| 境界層該当者 | 0円 | 100円 | 110円 | 110円 |
- ※生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものの額は、一日3食に相当する額が限度となります。
- ※入院時生活療養費Ⅰと入院時生活療養費Ⅱのどちらかを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、入院されている医療機関にお問合せください。
- ※「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について、1食100円(令和6年6月1日以降は1食110円)、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方のことです。
4保険外併用療養費
保険制度では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、その医療費の全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣が定める「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」については、保険診療と保険外診療の併用が認められ、保険診療に該当する基礎的部分の保険者負担相当額を保険外併用療養費と呼んでいます。
患者は、保険で認められていない高度先進医療や未承認薬等の費用の全額と、保険診療に該当する基礎的部分に対する自己負担分を、医療機関等の窓口で支払います。
| 評価療養 | 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他療養であって保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの 例:先進医療、医薬品の治験にかかる診療など |
|---|---|
| 患者申出療養 | 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
例:未承認薬などをいち早く使いたい、対象外になっているが治験を受けたいなどの患者の要望に対応するための制度 |
| 選定療養 | 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養のもの 例:差額ベッド、時間外診療、制限回数を超える医療行為など |
5長期収載品の処方又は調剤に係る選定療養における患者の特別負担について
令和6年10月1日から、患者が後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたいと希望した場合に、一定の条件に該当する場合、この差額の4分の1を患者が負担する仕組み(選定療養)が導入されました。
詳細は、厚生労働省のホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご参照ください。
なお、選定療養における「特別の料金」については、健康保険適用外となるため、毎年、当組合から送付申し上げる「医療費通知」記載の「医療費の総額、弁護士国保組合の支払い額、国等からの支払い額、加入者の支払い額」には反映されません。
このため、選定療養における「特別の料金」を医療費控除で申告される場合は、医療機関・薬局からの領収書を保管いただき、「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費等の領収書は確定申告期限から5年保存する必要があります)のでご注意ください。