保険料について
- 目次のリンク先から戻る際は、右下に表示される「PAGE TOP」をご利用ください。
- 東京都弁護士国民健康保険料の簡易計算表
- 1.保険料について(令和7年度)
- 2.保険料納付方法等について
- 3.保険料の納付が遅れた場合
1保険料について(令和7年度)
| 保険料月額 | 月額内訳 | |
|---|---|---|
| 1介護保険賦課被保険者※でない組合員 | 31,600円 (年額379,200円) |
|
| 2介護保険賦課被保険者である組合員 | 37,300円 (年額447,600円) |
|
| 3介護保険賦課被保険者でない家族 1人につき |
13,400円 (年額160,800円) |
|
| 4介護保険賦課被保険者である家族 1人につき |
19,100円 (年額229,200円) |
|
- ※介護保険賦課被保険者とは40歳から64歳の加入者です。
- ※資格取得手続き後、初回の納入については、資格取得の届出月の翌月に加入月からの保険料について納入通知書を送付いたします。
- ※追加加入・資格喪失・一部喪失の手続きがあった場合および新たに40歳に到達し、介護納付金賦課被保険者となった場合は届出月および該当月 の翌月に納入通知、還付通知を送付しております。
(1)産前産後期間相当分の保険料軽減措置
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日より、出産する予定の被保険者または出産した被保険者について、産前産後期間における国民健康保険料を免除いたします。
1.対象となる方
令和5年11月1日以降に出産、または出産予定の被保険者
- ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります。(死産・流産・早産及び人口妊娠中絶を含む。)
2.免除となる保険料
出産する被保険者本人の基礎賦課額・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額
3.免除となる期間
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)翌々月(以下「産前産後期間)といいます。)までの保険料が免除されます。
- ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。
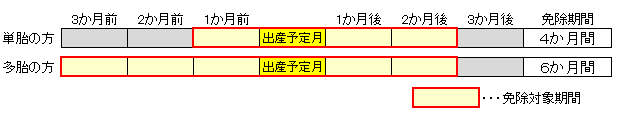
4.届出方法・必要書類
次の書類を当組合に郵送にてご提出ください。
- ①産前産後の保険料軽減措置届出書
- ②母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日のページ)
- ※出生後は、母子健康手帳の出生届出済証明があるページの写し、出生証明書の写し、または「世帯全員」と記載がある住民票の写し(いずれか1点)
- ※流産死産の場合は、医師の診断書等(在胎日数がわかるもの)
- ※多胎妊娠の場合は2人分必要です。
5.届出受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。
例) 出産予定日が令和6年6月1日の場合、届出は令和5年12月1日からの受付となります。
- ※保険料の納付期限の翌日から起算して2年を経過した日以後の保険料の軽減決定はできません。
6.その他
- 免除対象期間の保険料が既に納入されている場合は、還付となります。保険料の口座振替をご利用の方は、該当金融機関の口座に還付します。別口座に還付を希望される場合は当組合にご連絡ください。
口座振替を利用されていない方は、届出の指定口座に還付となります。 - 原則として届出が必要ですが、届出がない場合でも出生による追加加入や出産育児一時金支給申請に基づき、当組合で保険料軽減決定する場合があります。
-
出産予定日と出産日が相違した場合、出産被保険者等の負担軽減を図るため、原則として保険料の変更賦課等は行いません。なお、組合員から修正申告があり、産前産後期間の変更に伴う減額調定の額に変更がある場合には再算定を行います。
(2)未就学児世帯支援金
4期分(1月~3月分)の保険料額から未就学児1人につき12,000円を控除して請求致します
未就学児世帯支援金は、「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)を踏まえ、子ども・子育て支援の拡充として、公営国保の未就学児に係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置が導入されたことを受け、国保組合についても、令和3年12月27日の令和4年度予算編成通知で、特別調整補助金の一部として未就学児1人につき12,000円の財政支援を行うとされました。
それを受けて、未就学児世帯支援金を4期分(1月から3月分)の保険料に充当することで、4期分の保険料額から未就学児1人につき12,000円を控除して請求致します(十一月三十日時点の未就学児である被保険者が属する組合員の世帯のうち当該年度の一月一日に被保険者資格がある組合員が対象です)。
2保険料納付方法等について
(1)納期
保険料は1年度を次の四期に分けて納入いただいております。納付期限内の納付についてご協力の程お願いいたします。
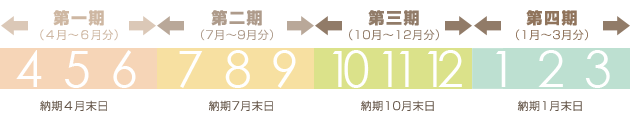
(2)保険料納付方法
- 口座振替(振替手数料は組合が負担いたします)
「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、弁護士国保にご提出ください。
(※1)直接、金融機関への申込みはできません。
(※2)印刷用紙はA4・白色をご利用ください。
(※3)提出いただいた振替依頼書は返却しませんので、必要な場合は、ご自身でコピーをお取りください。
都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、農協、労働金庫の全行およびゆうちょ銀行が利用できます(農協については一部取扱不能先があります)。なお、神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会の方は全員、口座振替にて納入をお願いしております。また振替日は納期月 の25日もしくは27日(銀行休業日の場合は翌営業日) となります。なお、銀行が、土、日休業となっておりますので、月曜日が振替日の時は、前の週の金曜日までに口座に振替額をご用意ください。 - 銀行振込みの場合(振込手数料は組合員がご負担くださいますようお願いします)
次の銀行の東京都弁護士国民健康保険組合の口座(略称─「弁護士国保」の口座)にお振込みください。取引銀行
みずほ銀行 東京中央支店 当座預金-0006890
三井住友銀行 赤坂支店 当座預金-0015116
三菱UFJ銀行 京橋支店 当座預金-2594742 - 保険料納付方法の変更
- ①銀行振込みから口座振替に変更の場合
「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、弁護士国保にご提出ください。
(※1)直接、金融機関への申込みはできません。
(※2)印刷用紙はA4・白色をご利用ください。
(※3)提出いただいた振替依頼書は返却しませんので、必要な場合は、ご自身でコピーをお取りください。 - ②口座振替を銀行振込みに変更の場合
「事務所等変更届」の「変更前」「その他」欄に「口座振替」、「変更後」「その他」欄に「銀行振込み」と記載してお届けください。なお、従来より、神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会の方は全員、口座振替にて納入をお願いしております。
- ①銀行振込みから口座振替に変更の場合
(3)その他
- 銀行振込み、口座振替の場合、領収書は、改めて発行しておりませんのでご了承ください。
- 銀行の合併にともない、同一口座からの複数の組合員の保険料を引落しの場合、申込時期により振替日および通帳への記帳内容が相違することがあります。
- 国民健康保険料納付証明書については、毎年12月に送付いたします。納付証明書を送付後、12月中に納付があった場合には、その金額を含めたものを再送付いたします。
- 被保険者の資格取得、資格喪失により保険料の算定基礎が変更となります。資格取得・資格喪失については必ず14日以内に、所定用紙にご記入のうえ、必要書類を添付して組合事務局に手続き下さるようお願いいたします。
なお、資格取得・資格喪失の届出日(事前の書類預かりの場合は資格喪失日)の翌月に取得分の保険料の請求、翌月末に喪失分の保険料の還付を行います。
組合員がお亡くなりになった場合の保険還付の申請は、こちら「組合員が亡くなった場合の給付金・保険料の還付金の申請について」 をご覧ください。 - 組合事務局に現金ご持参による納入はご遠慮いただいております。銀行振込みにて納入をお願いいたします。
3保険料の納付が遅れた場合
保険料は皆様が医療機関にかかるときの医療費等に充てられる大切な財源ですので、納付期限までに納付いただきますようお願いします。
(1)保険料の納付期限は賦課月の月末となります
納付期限を過ぎた場合や残高不足等で口座振替がされなかったときは、「国民健康保険料 未納のおしらせ」を送付しますので、振込みで納付をお願いします。
(2)督促状
「国民健康保険料 未納のおしらせ」の指定期日を経過後も納付がない場合は、組合規約に基づき、「国民健康保険料 督促状」を送付します。督促状が送付されると、督促手数料が加算されます。また、督促状に記載の指定期日を過ぎると、延滞金が発生する場合があります。
(3)保険料を6か月以上滞納した場合
正当な理由がないのに保険料を6か月以上滞納した場合は、組合規約第九条に基づき、当組合を除名となる場合があります。
組合規約抜粋
(除 名)
第 九 条 次の各号の一に該当する組合員は理事会の議決によって除名することができる。
一 正当な理由がないのに保険料の納付期日後六ケ月を経過したにもかかわらず保険料を納付しないとき。
(4)滞納処分
保険料の滞納が続くと、国民健康保険法第八十条に基づき、滞納処分(財産の差し押さえ等)を行う場合があります。
- ※保険料納付についての相談等がありましたら、組合事務局までご連絡ください。
Column
- 参考:東京都杉並区国民健康保険の保険料率(令和7年度)
杉並区の料率については杉並区のホームページでご確認ください。
医療給付分に対する保険料(賦課限度額66万円)
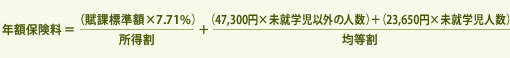
後期高齢者支援金分に対する保険料(賦課限度額26万円)
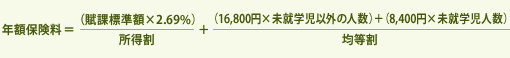
介護分に対する保険料(40歳から64歳の介護保険第2号被保険者の方のみ賦課、賦課限度額17万円)

- *賦課標準額とは、令和6年の所得の「旧ただし書き所得」となります。
- *世帯で合算した所得金額が一定の基準以下の場合は均等割額が減額されます。
- *「旧ただし書き所得」とは・・・
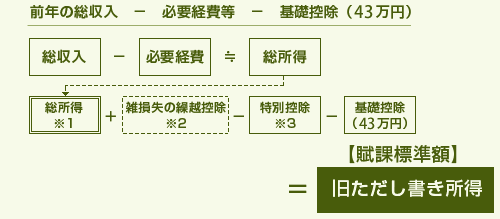
- ※1 退職所得は、保険料算定の対象となる総所得金額等に含みません。
- ※2 雑損失の繰越控除額は、旧ただし書き所得では控除の対象になりません
- ※3 分離長期・短期譲渡所得に係る特別控除額は、控除の対象になります。
- *各自治体の保険料率は異なりますので、居住地の区市町村にお問い合わせください。